
2022年の「社会保険の適用拡大」を正しく理解して、働き損にならないように対策しましょう!
社会保険の扶養のボーダーラインである「130万円の壁」について以前ご紹介しました。
パート年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れて、自分で社会保険料を納付しなければいけませんよね。
でも2022年10月からは、短時間労働者(パート)の社会保険適用が拡大されることが決まっています。
具体的には、社会保険適用の条件が年収106万円に引き下げられ、社会保険適用対象となる対象者が大きく増えることになります。

え?2022年10月ってもうすぐじゃない?私は条件に当てはまるのかしら?
社会保険の適用の拡大は、年収106万円に加えて、諸々の条件に当てはまった場合にのみ対象になります。
そしてその条件が、2022年と2024年に段階的に変わります。
現在130万円の壁を基準に働いている人にとっては、今後自分が106万円の壁の対象になるのか、いつの段階で対象になるのか、気になるところですよね?
というわけで、社会保険対象適用の「106万円の壁」について詳しく解説していきます。
- 現在社会保険の扶養内で働いていて、今後もそうしていく予定の人
- 現在社会保険の扶養内で働いているけど、今後扶養を外れることも検討している人
- これからパートをしようと思い、扶養内にするかどうか考えている人
- 自分が106万円の壁に関係するかどうか気になっているパートタイム勤務の人
このような方の参考になれば幸いです。
その他、「主婦と仕事」に関する最新の総合記事はこちらです▼
パート収入「106万の壁」とその条件とは?
「106万円の壁」とは、社会保険料の支払い義務が発生する年収のボーダーラインです。

あれ?社会保険料の支払いの義務って、130万円の壁じゃなかったっけ?
厳密にいうと、130万円の壁は社会保険の扶養から外れる上限年収で、106万円は条件によって社会保険に加入する義務が発生する年収境界です。
2つの壁は、微妙に違うのですが、結果として、社会保険の扶養から外れて自分で社会保険料を納付するという点は同じです。
106万円が、社会保険加入の境界線になる条件は、下記のような項目で決まります。
- 条件1:1週間の労働時間
- 条件2:月額収入の金額
- 条件3:勤務期間
- 条件4:勤務先の従業員数(厚生年金の被保険者数)
- 条件5:学生かそうではないか
パートタイムなどの時間労働者が増えていることから、上記の条件を段階的に変えて、社会保険の適用者を増やそうというのが、社会保険の適用拡大です。
106万の壁の条件はこう推移する
106万の壁|2021年現在の条件
まずは2021年現在の106万円の壁の条件について確認していきましょう。下記の5つすべての条件が当てはまる人のみ、106万円の壁の対象になります。
条件1:労働時間が週20時間以上
労働時間が週に20時間以上、これが条件のひとつです。
正社員の労働時間40時間の半分が目安ですね。
自身の1週間の勤務時間を確認してみましょう。
条件2:月額収入が8.8万円以上
年収106万円を月額換算すると、おおよそ8.8万円。
「106万円の壁」と言われているものの、実際には月収8.8万円以上あるかどうかという金額で判断されます。
年収106万円はあくまで目安で、気にする必要があるのは月収8.8万円のボーダーラインと考えてください。
掛け持ちの場合は合算です。
条件3:勤務期間が1年以上の見込み
勤務期間が1年以上ある、またはその見込みであることも条件の1つです。
労働時間や月収の条件をクリアしていても、3ヶ月や6ヶ月など1年に満たない短期契約の場合は、106万円の壁は適用されません。
短期契約でも、契約更新の可能性があることが契約書に記載されていれば、「1年以上の勤務期間の見込みがある」と判断されます。
条件4:勤務先の従業員が501人以上
勤務先の規模も条件の1つで、2021年現在は従業員数が501人以上の企業に勤めている事が適用条件になっています。
「従業員数」は働いている人数ではなく、厚生年金の被保険者数のみで計算します。
ただし、従業員数が500人以下の場合でも、下記2つのケースでは106万円の壁が適用されます。
- 地方公共団体に所属している場合
- 労使合意を結んでいる場合
労使合意とは、雇用主と労働者の過半数が社会保険に入ることについて合意することです。雇用主が合意した旨を年金事務所に届け出ます。
条件5:学生ではないこと
学生でアルバイトをしている場合は、106万円の壁は適用外です。
ただし、定時制や夜間学校の学生などの場合は加入対象となる可能性もあります。

106万円の壁が適用されるのは、上記5つの条件をすべて満たす場合だけです。基本的に学生さんは気にする必要はありません。
106万の壁|2022年(令和4年)からの条件
冒頭でも説明した通り、この106万円の壁の条件は、2022年(令和4年)10月に変更されます。
変更点と言うのは、5つの条件のうち「条件3:勤務期間」と「条件4:勤務先の従業員数」の2つです。
変更点1:勤務期間が1年→2か月以上の見込みに
これまで要件となっていた「1年以上の雇用期間が見込み」は、改正法で撤廃されることとなりました。
2022年(令和4年)の施行後は、フルタイム勤務と同様に「2ヶ月以上の雇用見込みがあること」が社会保険の加入条件となります。

1年から2か月になったことで、短期契約の場合も適用されるようになりました。
変更点2:勤務先の従業員が501人以上→101人以上
これまで従業員(厚生年金の被保険者数)の総数が常時501人以上の企業が対象だったものが、2022年には「101人以上の企業」となりました。
今まで大企業の従業員だけが対象になっていましたが、今後は中規模の会社の従業員にも社会保険の支払い義務の上限年収が引き下げられることになります。
106万の壁|2024年(令和6年)からの条件
社会保険加入の段階的拡大の最後2024年(令和6年)には、従業員の規模が101人以上から51人以上にさらにすそ野を広げます。
多くの中小企業のパート従業員が、2024年(令和6年)以降は106万円の壁の対象となる見込みです。
106万円の壁条件の推移
| 2022年9月まで | 2022年10月から | 2024年から | |
|---|---|---|---|
| 条件1:1週間の勤務時間 | 20時間以上 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 条件2:月額収入 | 8.8万円以上 | 8.8万円以上 | 8.8万円以上 |
| 条件3:勤務期間 | 1年以上 | 2ヶ月以上 | 2ヶ月以上 |
| 条件4:勤務先の従業員数 | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
| 条件5:対象者 | 学生は対象外 | 学生は対象外 | 学生は対象外 |
年収が106万超えたらどうなる?
106万円の壁を越えても、すべての条件に当てはまらなかったら?
ここまで、「年収106万円の壁」の意味と、その対象者となる条件の今後の拡大についてみてきました。
もし仮に、年収が106万円を超えていたとしても、その他の条件が1つでも当てはまらない場合はどうなるのでしょうか?
この場合、社会保険加入の義務はなく、年収130万円までは配偶者や親の社会保険の扶養に入ることができます。
ただし、年収130万円を超えると、すべての人が社会保険の扶養から外れ、国民年金や国民健康保険、または会社の厚生年金や厚生年金保険に自分で加入する必要があります。

106万円の壁の対象者以外の全員が130万円の対象者です。130万円が社会保険の扶養の最終ボーダーラインですね。
106万の壁を超えたときのデメリット
では次にに、5つの条件全てを満たし、パート年収が106万円を超えてしまったらどうなるのでしょうか?
まずは「デメリット」から解説します。
社会保険料の負担で手取り年収が減る
社会保険料が毎月天引きされるようになることで、働いた分よりも当然手取りは減ります。
年収が105万円と107万円の時では、ざっくりとした計算でもこんなにも手取り金額が変わります。
| 年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 | 手取り金額 |
|---|---|---|---|---|
| 105万円 | 8000円 | 2000円 | 0円 | 約104万円 |
| 107万円 | 8000円 | 4000円 | 16万円 | 約90万円 |

106万円の壁を少し超えたくらいの金額が、一番働き損になってしまうってことね!ここまで変わるなら、106万円の壁はしっかり年収を抑えるか、超えるなら大きく超えるようにした方がよさそうね。
労働時間が増える
単純に、106万円に抑えて働くのと、106万円を超えて働くのとでは、労働時間が増えます。
106万円の壁の条件は、週20時間以上です。
子育てママにとっては、この労働時間の確保は大きな負担になる人も多いはずです。

労働時間が増えて大変になったのに、手取り収入が減るなんて辛すぎるわね!それなら無理のない時間でゆったり働きたいわ!
会社からの手当てに影響を及ぼす
公的な制度ではなく、会社の福利厚生として支給される家族手当等の支給基準を、一般的に健康保険の扶養資格としている会社も多いです。
現在は130万円としていても、今後の社会保険の拡大によって106万円になる会社も出てくる可能性があります。
そうなって手当てを受ける資格がなくなれば、支給されていた手当分も配偶者の年収が目減りすることになります。
106万の壁を超えたときのメリット
確かに、保険料負担や手当の打ち止めは痛手ではありますが、社会保険料負担はデメリットばかりではありません。もちろんたくさんメリットもあります。
単純に世帯年収が増える
106万円以上の金額を稼げばその分単純に世帯年収が増えます。
106万円をほんの少し超えるような場合は手取りの減り方が大きく損に思いますが、大きく超えて働くことになればその分収入は増加しますね。
労働時間をしっかり確保できる場合、たくさん働きたいという意思がある場合は、106万円の壁を大きく振り切って働くのが得策です。
年金額が増える
厚生年金の扶養に当たる国民年金の「第3号被保険者」は、65歳になってから受け取れる年金は「老齢基礎年金」という、年金制度の1階部分のみです。
しかし、厚生年金を自分で負担することで、「報酬比例」の2階部分の年金もプラスで受け取れるようになります。
また、「障害年金」に関しても障害基礎年金だけではなく、障害厚生年金がプラスで受け取れます。
障害基礎年金は障害等級2級までに対し、障害厚生年金は3級まで認めらるので、受給の範囲が広くなります。
傷病手当金と出産手当金が受け取れる
健康保険は、実は被扶養者と被保険者では異なる扱いがされる制度があります。
それが、「傷病手当金」と「出産手当金」です。
被扶養者の場合は受け取れませんが、自分で保険料を納めている場合、傷病や出産で会社を休んだ際には、健康保険から給料の3分の2相当の手当金が支給されます。

自分で保険料を払うということは、様々な保障を手厚く受けられるってことです!老後の不安や失業の不安があるなら、106万円を超えてしっかり社会保険料を納めるのもいいかもしれません。
結局何が得?どうしたらいいの?
ここまで、106万円の壁を超えるメリットとデメリットを紹介してきました。
各家庭の事情や働けるリソースにも個人差があるため、最終的に自分にとって何が得かで判断する必要があります。
それでも「106万円の壁を超えるか超えないか、自分にとってどちらが良いのかわからない」と悩んでだ時は、下記の2つの壁も参考にしてみるといいと思います。
106万円の壁を超えたら訪れる「150万円の壁」「201万円の壁」
106万円の壁を越えて社会保険の対象となるときは、税制の方の扶養である配偶者特別控除の「150万円の壁」「201万円の壁」も意識しましょう。
150万円の壁は、配偶者特別控除が減り始める基準で、201万円の壁は配偶者特別控除の対象を外れるボーダーラインです。
ただ、配偶者の年間所得が1000万円を超える場合は、どのみち対象外ですので気にする必要はありません。
配偶者控除と配偶者特別控除は、下記にまとめました。
106万円の壁を超えないなら「103万円の壁」「100万円の壁」
106万円の壁を超えない場合は、「103万の壁」「100万円の壁」も視野に入れるといいと思います。
「103万円の壁」は所得税の課税対象、「100万円の壁」は住民税の課税対象となる年収です。
扶養内で働くのは、社会保険だけでなく、税制度の面での考慮も必要です。
106万円の壁は超えると手取りは減り、保障が充実
ここまで、2022年に社会保険の対象拡大政策によって、対象者が増える「106万円の壁」について解説しました。
106万円の壁は、超えると社会保険料の負担によって手取り額が減りますが、年金や保険などの保障が手厚くなりますます。
106万円の壁には5つの条件があり、すべて満たした場合にしか適用されない点も要注意です。
超えるかどうか迷ったときは、「手取り金額」「働く時間」「受けられる保障」を加味して、ライフスタイルをシミュレーションしてみるといいかもしれません。
106万をうまく調整する裏技
106万円の壁を超えるにしろ超えないにしろ、少しでもお得に多くの収入を手元に残したいですよね。
そこで、最後に106万円の年収をうまく調整する裏技を紹介したいと思います。
106万円の壁を越えない場合の裏技
106万円を超えない場合のデメリットとして、ギリギリいっぱい働きたいと言っても、会社の都合で思うように働けず、稼げないという問題があります。
パートで十分稼げない分、掛け持ちするのもアリですが、労働時間を調整するのが難しいですね。
そんな時は、副業など、自分の空き時間や趣味などを生かした働き方を追加するのがおすすめです。
106万円の壁を超える場合の裏技
社会保険は1人1保険が原則です。
パート先で社会保険に加入している方は、その1か所の収入のみによって保険料が決まります。
つまり、パート先の収入を106万円ちょっとに保って働けば、社会保険料は最低限の金額で済みます。
そのうえで副業を行えば、社会保険料が増えることなく手取り収入が増えます。
パート収入が増えてしまえば社会保険料も増えますが、副業での収入が増える分には、保険料の負担は変わらないという裏技です。

賢く副業も取り入れて、収入を増やしましょう♡
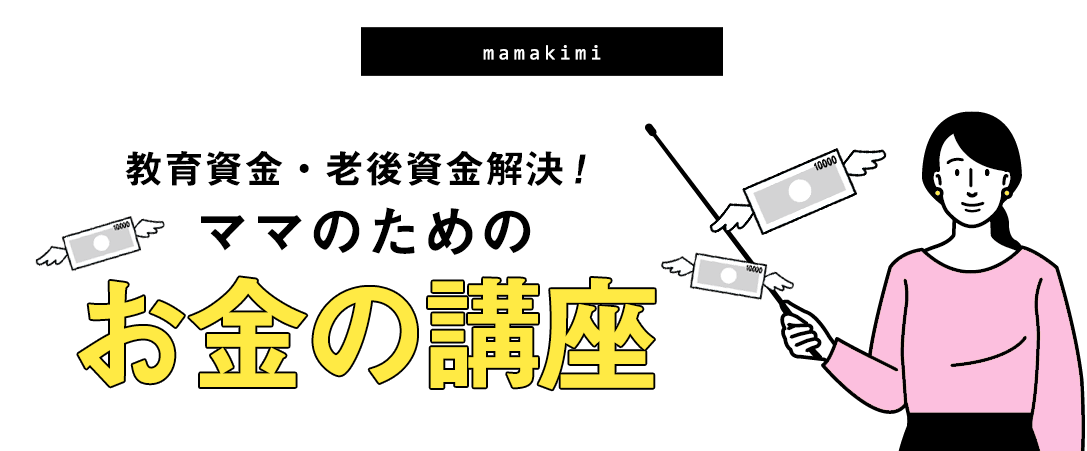
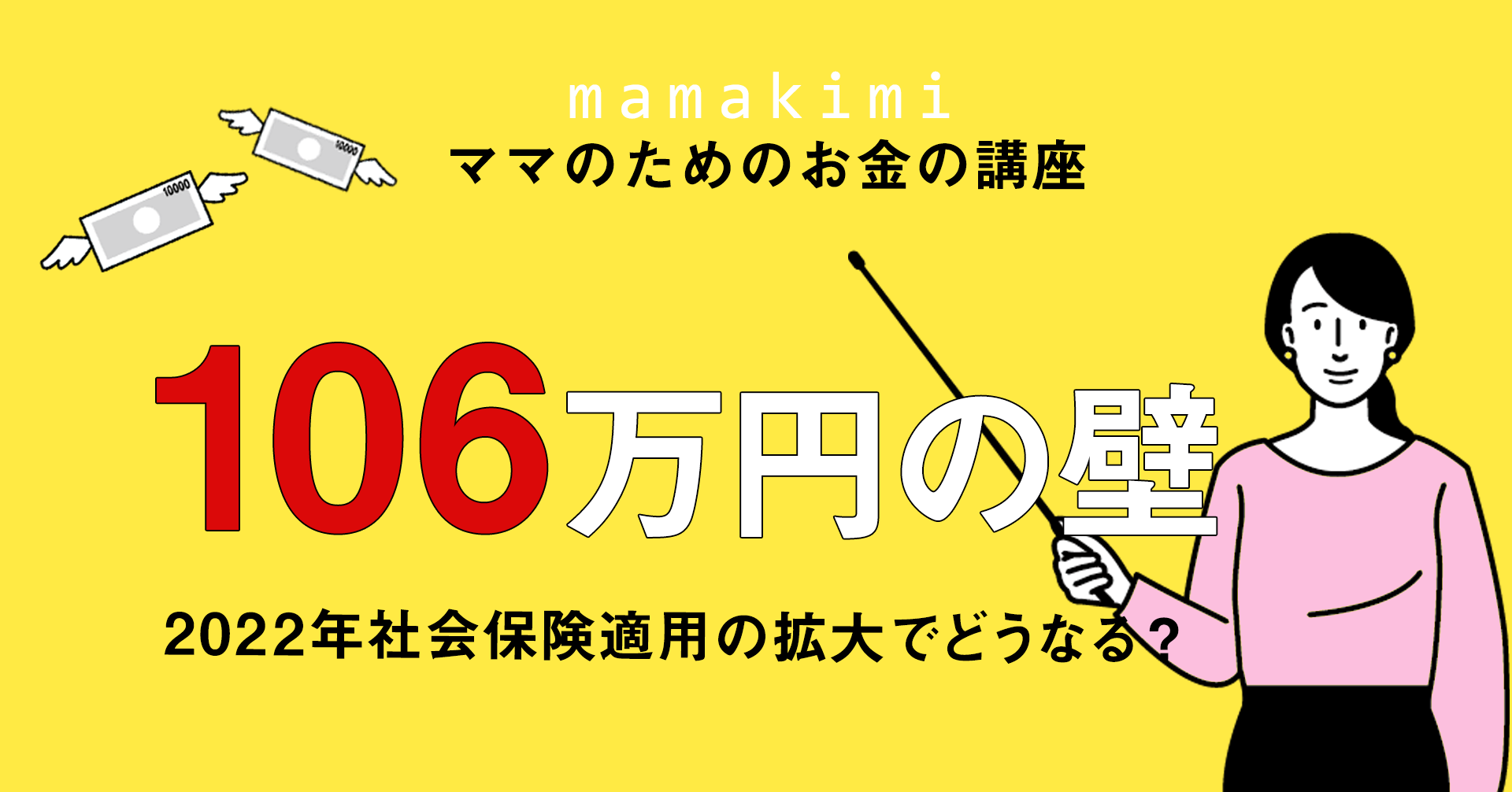
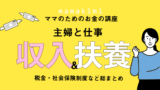
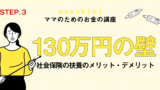
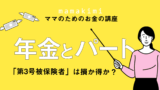
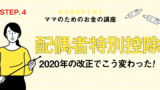
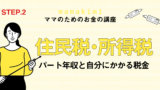
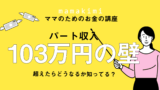
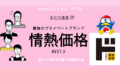

コメント