
「配偶者控除」、、、。制度の存在は知っているけど、その詳しい内容や、メリットの最大化方法がわからない。そんなもやもやをスッキリさせましょう!
扶養の範囲内でパートをする際、所得税や住民税で控除の恩恵を受けるために収入を抑える「○○万円の壁」を越えない働き方。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、この扶養と年収の壁に密接に関わっています。
「配偶者控除」という言葉自体は聞いたことがあるけれど、「配偶者特別控除」との違いや、その詳しい内容を把握していない人もいらっしゃるでしょう。
2020年に制度も変わり、控除が受けられる範囲や金額も変わりましたので、余計に混乱してしまいますよね。
今回は、そんな「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について、内容や違いについてわかりやすく、詳しく解説したいと思います。
- 配偶者の居る納税者が対象の制度
- どちらの制度も「住民税」と「所得税」に対してそれぞれ受けられる所得控除制度
- 「配偶者控除」が対象外の場合に適用されるのが「配偶者特別控除」
- 納税者本人と、配偶者がそれぞれの条件を満たす場合に受けられる控除
- 直近では2018年と2022年に制度が改正されている
- 年間所得1,000万円(給与所得者で年収1,195万円)以上からはいずれの制度も対象外
「主婦と仕事」に関する最新の総合記事はこちらです▼
「所得控除制度」とは?
所得税や住民税と言った税金は、「課税所得」をベースに計算されています。
課税所得と言うのは、イコール会社から支給される給料ではありません。
給料から、「基礎控除」「扶養控除」「雑損控除」「寄付金控除」など、様々な控除を差し引いたて残った金額が「課税所得」になります。
課税所得=給料(年収)-所得控除
この所得控除の種類の中に「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。

支払う税金を減らして手取り金額を増やすには、所得控除が少しでも多く受けられる方がいいってことよね!
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者特別控除は、配偶者控除の適用枠を超えた場合も、段階的に所得控除を受けられるように、平成15年の税制改正時に今の形をとるようになりました。
(※平成15年以前の配偶者特別控除は、配偶者控除に上乗せする部分を段階的にするものでした)
その違いは、所得税・住民税の控除条件と控除される金額にあります。
本来パート収入が103万円までの場合に受けられる「配偶者控除」ですが、1円でもオーバーすると控除対象外になります。
この制度をカバーし、控除額を段階的に0にしていく調整を「配偶者特別控除」が担っています。

「配偶者控除」を受けられる人はこの制度を受け、自分のパート年収の問題で配偶者控除の対象外になった場合は「配偶者特別控除」の対象になる、と認識しておくといいですね。
配偶者控除とは?
「配偶者控除」は、配偶者をもつ納税者が受けられる所得控除で、この控除を受けるにあたっては、納税者本人と配偶者が所定の条件を満たす必要があります。
配偶者控除を受ける条件
配偶者控除の対象となる配偶者を「控除対象配偶者」といいます。
配偶者控除を受けるには、納税者本人に対する条件と、「控除対象配偶者」となる条件、すべてを満たしている必要があります。
- 合計所得金額が1,000万円以下であること
※「合計所得金額」とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、公的年金等に係る所得などの「総合所得」を合計した金額で、純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額を指します。給与収入のみであれば「給与所得控除」を差し引いた金額になるので、最大1195万円になります。
①法律上の配偶者であること
内縁関係や同性婚などの事実婚の妻(夫)については、現行制度では控除対象配偶者の対象外となっています。
②納税者と生計を一にしていること
「生計を一にしている」とは、同じ収入源で暮らしていることです。基本的には「同居」が基準となりますが、単身赴任などで別居している場合、生活費の仕送りなどの状況があれば「生計を一にしている」という条件に当てはまります。
③合計所得金額が年間48万円以下であること
配偶者の合計所得が48万円。これは、パートなどの給与収入である場合、給与所得控除の55万円を足して年収103万円以下ということになります。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
青色事業専従者給与や専従者控除などとは重複して控除を受けることができないということです。
上記5つの全ての条件を満たしている場合にのみ、配偶者控除が適用されます。
配偶者控除の控除金額
配偶者控除は、国税である所得税と、地方税である住民税それぞれにあり、控除される金額が異なります。
そして、控除対象配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」と言う扱いになり、控除金額が異なります。

子育てママ世代には関係ないかもしれませんが、子供が巣立つ今後のために、一応「老人控除対象配偶者」の金額も載せておきます。
| 納税者の 合計所得金額 | 所得税配偶者控除額 | 所得税老人控除額 | 住民税配偶者控除額 | 住民税老人控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円~ 950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円~ 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 11万円 | 13万円 |
| 1,000万円以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
納税者の所得を3段階に分けて、控除される金額が段階的になっています。
いずれにしても、納税者の合計所得が1,000万円を上回る場合には、配偶者控除の対象外となります。
配偶者特別控除と150万円の壁・201万円の壁とは?
合計所得48万円(給与収入103万円)を1円でも超えてしまった場合、直ちに「配偶者控除」の「控除対象配偶者」ではなくなり、控除が0になってしまいます。
これを「103万円の壁」と言いますが、この配偶者控除の上限に囚われた働き方を是正すべく、103万円を超えても控除が0にならないよう、納税者と配偶者の所得に応じて段階的に一定額の所得控除をする仕組みが、「配偶者特別控除」です。
2018年、働き方改革の一環としてこの配偶者特別控除を拡大する改正がなされました。
更に2020年に、配偶者の合計所得金額が38万円以下から48万円以下と変更になりました。
同時に、給与所得控除が65万円から55万円になったことで、給与収入103万円の合計金額に変わりはありませんが、フリーランスや不動産など給与以外の所得を得ている配偶者にとって、控除条件が拡大される有利な改正となりました。
配偶者特別控除を受ける条件「201万円の壁」
配偶者特別控除の対象となる納税者の条件と、控除対象配偶者となる条件は、配偶者の年収以外は基本的に同じです。
- 合計所得金額が1,000万円以下であること
①法律上の配偶者であること
②納税者と生計を一にしていること
③合計所得金額が年間48万円以上133万円以下であること
パートなどの給与収入である場合、給与所得控除の加味して年収103万円超201万6,000円未満になります。これが配偶者特別控除の上限額「201万円の壁」の正体です。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
⑤配偶者自身が配偶者特別控除を受けていない事
配偶者控除は、夫婦どちら吉報しか受けることができません。
配偶者特別控除が適用されるのは、上記6つの条件を満たしている場合です。
給与収入が201万6000円を超えると、配偶者特別控除の対象からも外れ、控除がゼロになります。「201万円の壁」とは、このことを指して言われています。
配偶者控除の控除金額と「150万円の壁」
下記は、配偶者特別控除の控除金額です。
配偶者の所得金額と、納税者本人の所得に応じて、控除金額が段階的になっています。
また、所得税と住民税でも控除額が異なります。
| 配偶者の合計所得金額 | 給与収入換算 | 納税者所得900万円以下 | 900万円~ 950万円 | 950万円~ 1,000万円 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48万円~95万円 | 103万円超 150万円以下 | (所得税)38万円 (住)33万円 | 26万円 22万円 | 13万円 11万円 | 0円 0円 |
| 95万円~100万円 | 150万円超 155万円以下 | (所得税)36万円 (住民税)33万円 | 24万円 22万円 | 12万円 11万円 | 0円 0円 |
| 100万円~105万円 | 155万円超 160万円以下 | (所得税)31万円 (住民税)31万円 | 21万円 21万円 | 11万円 11万円 | 0円 0円 |
| 105万円~110万円 | 160万円超 166.8万円未満 | (所得税)26万円 (住民税)26万円 | 18万円 18万円 | 9万円 9万円 | 0円 0円 |
| 110万円~115万円 | 166.8万円以上 175.2万円未満 | (所得税)21万円 (住民税)21万円 | 14万円 14万円 | 7万円 7万円 | 0円 0円 |
| 115万円~120万円 | 175.2万円以上 183.2万円未満 | (所得税)16万円 (住民税)16万円 | 11万円 11万円 | 6万円 6万円 | 0円 0円 |
| 120万円~125万円 | 183.2万円以上 190.4万円未満 | (所得税)11万円 (住民税)11万円 | 8万円 8万円 | 4万円 4万円 | 0円 0円 |
| 125万円~130万円 | 190.4万円以上 197.2万円未満 | (所得税)6万円 (住民税)6万円 | 4万円 4万円 | 2万円 2万円 | 0円 0円 |
| 130万円~133万円 | 197.2万円以上 201.6万円未満 | (所得税)3万円 (住民税)3万円 | 2万円 2万円 | 1万円 1万円 | 0円 0円 |
| 133万円以上 | 201.6万円以上 | (所得税)0円 (住民税)0円 | 0円 0円 | 0円 0円 | 0円 0円 |
配偶者特別控除は、納税者の年収が900万円未満の時、配偶者の所得が95万円までは、配偶者控除と全く同じだけ控除を受けられます。
給与収入にして150万円になるので、「150万円の壁」と呼ばれています。

配偶者控除、住民税33万円・所得税38万円のマックス金額を受けられるのが、150万円というのが「150万円の壁」の概念ですね。
150万円の壁の落とし穴
150万円の壁は、配偶者の所得が48万円(給与収入103万円)を超えても95万円(給与収入150万円)までは、配偶者控除と同じ控除額が維持されるというものです。

じゃあ「103万円の壁」なんて言っていないで、150万円の壁ギリギリまで働いたほうがお得なんじゃないかしら?
しかし、それは納税者である一家の大黒柱の税金が増えないということにはなります。
ただ、パートをしている配偶者は所得が48万円(給与収入103万円)を超えると所得税の課税対象になります。
※住民税は各市区町村によって給与収入90万円台から課税されます。
150万円の壁は実質損?
配偶者控除、配偶者特別控除は税制度の控除の話でしたが、パートの年収に関わるのは税金だけではありません。
年金や健康保険といった社会保険制度にも、扶養の概念は存在します。
配偶者特別控除を満額受けるため、パート収入を150万円ギリギリに設定るると、この社会保険130万円の壁を越えてしまうため、社会保険料を自分で負担しなくてはいけなくなります。
130万円少し過ぎたくらいの年収になると、手取りが大きく下がる「働き損」状態になることがあり、「130万円の壁」として有名です。
税制度だけでなく、家計の全体の収入を見るて、配偶者特別控除の減少を気にせず150万円以上稼いでしまうか、103万円もしくは130万円以内に収めるかを考える必要があるということです。

「150万円の壁」よりも、「130万円円の壁」や「103万円の壁」の方が意識するべきだということがわかりますね。
パートで年収150万超えたらどうなる?
一方で、150万円の壁を越えてしまったらどうなるかを考えてみましょう。
150万円稼いでいる時点で、住民税・所得税に加え、社会保険料を納めているうえで、配偶者特別控除の控除額が、納税者の年収別に、下記のように段階的に引き下げられていくことになります。
| 給与収入換算 | 納税者所得900万円以下 | 900万円~ 950万円 | 950万円~ 1,000万円 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 103万円超 150万円以下 | (所得税)38万円 (住)33万円 | 26万円 22万円 | 13万円 11万円 | 0円 0円 |
| 150万円超 155万円以下 | (所得税)36万円 (住民税)33万円 | 24万円 22万円 | 12万円 11万円 | 0円 0円 |
| 155万円超 160万円以下 | (所得税)31万円 (住民税)31万円 | 21万円 21万円 | 11万円 11万円 | 0円 0円 |
| 160万円超 166.8万円未満 | (所得税)26万円 (住民税)26万円 | 18万円 18万円 | 9万円 9万円 | 0円 0円 |
| 166.8万円以上 175.2万円未満 | (所得税)21万円 (住民税)21万円 | 14万円 14万円 | 7万円 7万円 | 0円 0円 |
| 175.2万円以上 183.2万円未満 | (所得税)16万円 (住民税)16万円 | 11万円 11万円 | 6万円 6万円 | 0円 0円 |
| 183.2万円以上 190.4万円未満 | (所得税)11万円 (住民税)11万円 | 8万円 8万円 | 4万円 4万円 | 0円 0円 |
| 190.4万円以上 197.2万円未満 | (所得税)6万円 (住民税)6万円 | 4万円 4万円 | 2万円 2万円 | 0円 0円 |
| 197.2万円以上 201.6万円未満 | (所得税)3万円 (住民税)3万円 | 2万円 2万円 | 1万円 1万円 | 0円 0円 |
| 201.6万円以上 | (所得税)0円 (住民税)0円 | 0円 0円 | 0円 0円 | 0円 0円 |
ただ、税金や社会保険料などを差し引いても、やはり、稼げば稼ぐほど世帯収入は上がります。

控除額の大きさよりも、入ってくる収入ベースで考える方が、家計にとってはいいかもしれないわね。
201万の壁とは?
上記の表を見ての通り、配偶者特別控除は、所得税・住民税ともに、パート年収で言うところの201万6000円未満までしか控除がありません。
これを「201万円の壁」といいます。
201万円の壁とはつまり、配偶者特別控除を受けられるボーダーラインを意味します。
配偶者特別控除、201万円以上稼いだら損しかない?
「配偶者特別控除を受けられなくなるなんて損!」
そう考える人もいるかもしれませんが、130万円の壁を超え、社会保険料を自己負担する境界ほど、201万円以下と以上での金額差はありません。
控除額にして、住民税・所得税とも1~3万円程度だからです。

201万円の壁もそうですが、配偶者特別控除は納税者の年収も影響しますし、それぞれの家庭によって損得の分岐点も異なります。
制度を理解して、自分の家計にとって最適な働き方を見つけたいですね!
配偶者控除・配偶者特別控除と150万円の壁・201万円の壁のまとめ
- 「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに、配偶者の居る納税者が対象の所得控除制度
- どちらの制度も「住民税」と「所得税」に対してそれぞれ受けられる所得控除制度
- 「配偶者控除」が対象外の場合に適用されるのが「配偶者特別控除」
- 納税者本人と、配偶者がそれぞれの条件を満たす場合に受けられる
- 直近では2018年と2022年に制度が改正されている
- 150万円の壁は、配偶者特別控除で配偶者控除と同額の控除を受けられる境界
- 201万円の壁は、配偶者特別控除を受けられるボーダーライン
- 年間所得1,000万円(給与所得者で年収1,195万円)以上からはいずれの制度も対象外
配偶者控除、配偶者特別控除は度重なる改正の後、計算方法が複雑になっています。
控除対象となる納税者(旦那様)の所得とパートしようとする自分(控除対象配偶)の所得の両方で決まること、またそれぞれの壁には税制だけでなく社会保険の境界線をまたぐことも覚えておきましょう。

稼ぎ損にならない働き方のために、公的制度をマスターしましょう!
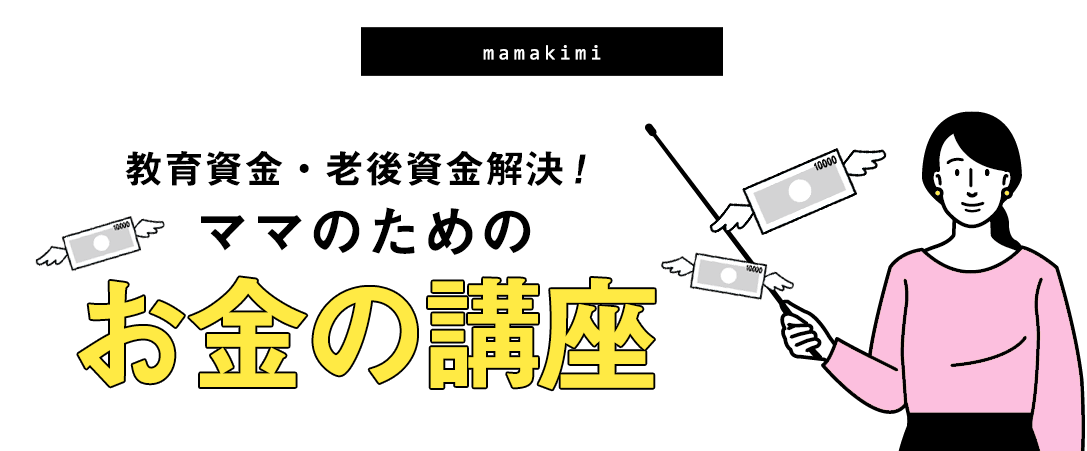
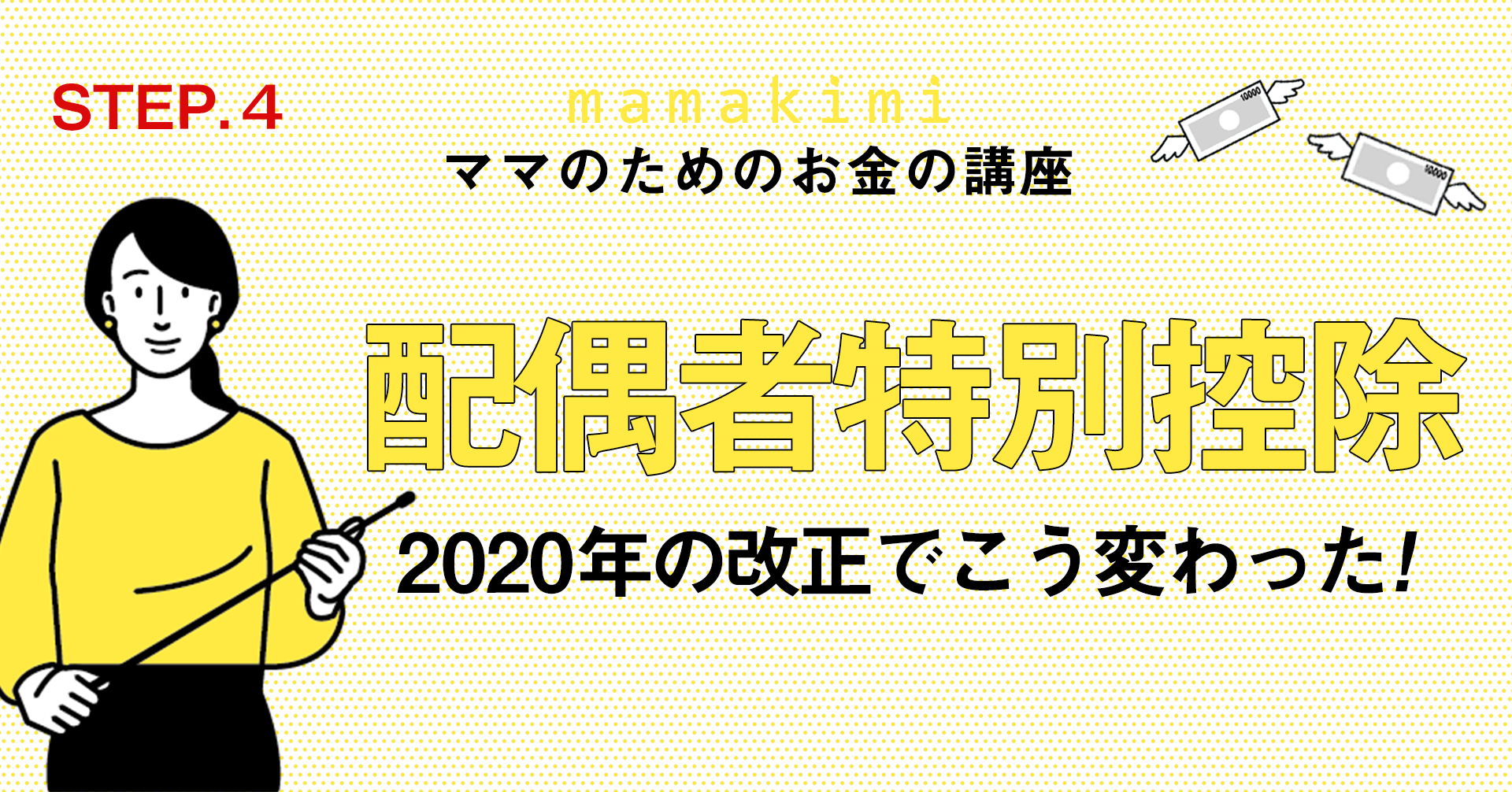
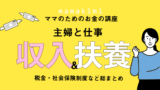
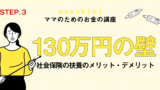
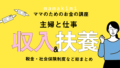
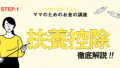
コメント