
子育てママのパート、扶養内で働くか扶養を外れるか、、、。迷っている方必見!年金と扶養について詳しく解説します。
社会保険の扶養の壁、106万円や130万円について、損か得かということはよく議論されますね。このブログでも過去に取り上げてきました。
今回は、その社会保険の中でも「年金」について、扶養と損得について検証していきたいと思います。
- 年金の扶養の制度をあまりよく理解していない
- パートで扶養を外れるかどうか迷っている
- 年金が被扶養者の場合、将来の年金の受取額の損得を知りたい
- 少しでも、将来の年金を増やせる方法を知りたい
- 自分が60歳を過ぎたとき、年金制度をどうすればいいのか知りたい
「主婦と仕事」に関する最新の総合記事はこちらです▼
年金と扶養の関係を解説
そもそも年金制度とは?と言うところからざっくりおさらいしていきましょう。
まず日本では、国内に在住する20歳以上60歳未満のすべての国民が国民年金制度(支給される際は「老齢基礎年金」)に加入することが法律で義務付けられています。
「厚生年金」の加入者も自動的に国民年金に加入しています。
国民年金(基礎年金)には、職業などに合わせて3つの加入区分があります。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
|---|---|---|---|
| 加入対象者 | 自営業者や学生 | 会社員や公務員 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
| 加入方法 | 加入者自身で各自治体に加入を届け出る | 勤務先が届け出る | 配偶者の勤務先が届け出る |
| 保険料の納付 | 加入者自身で払い込む | 給料から天引きされ、勤務先が支払う | – |
| 保険料負担 | 全額負担 | 勤務先と半々で負担 | 自己負担なし |
| 年金の受け取り | 老齢基礎年金(国民年金) | 老齢基礎年金(国民年金)+報酬比例年金(厚生年金) | 老齢基礎年金(国民年金) |
年金の扶養と「第3号被保険者」とは?
上記の表を見てわかるとおり、「年金の扶養に入る」と言うのは、会社員や公務員の配偶者が、「第3号被保険者」になることを意味します。
第3号被保険者は、自己負担で年金保険料を納めることなく、将来老齢基礎年金(国民年金)を受け取ることができます。
これは、配偶者が加入する年金制度が保険料を負担する仕組みになっているからです。

保険料を払わずに年金がもらえるなら、「第3号被保険者」になるのが一番お得ってこと?

でも、自営業者の妻では「第3号被保険者」にはなれないってことよね?
配偶者が自営業者の場合、その妻(夫)が専業主婦(夫)であったとしても、「第1号被保険者」として、自己負担で年金保険料を納める必要があります。
また、会社員や公務員の配偶者であったとしても、扶養に入るには年収などの条件があります。
年金の扶養とその条件
第3号被保険者になるには、下記の3つの条件を満たしている必要があります。
- 年齢が20歳以上60歳未満であること
- 第2号被保険者(会社員・公務員)に扶養されている配偶者であること
- 扶養される配偶者(妻)の年収が130万円未満であること
年金の扶養とパート収入
扶養される配偶者(妻)の年収が130万円未満であることが条件になっていますが、130万円未満であっても下記のような条件を満たす必要があります。
| 対象者 | 条件 |
|---|---|
| 配偶者と同居の場合 | 第2号被保険者の収入の半分未満であること |
| 配偶者と別居の場合 | 収入が仕送り金額未満であること |
| 社会保険加入義務が106万円万円で生じる対象者 | 130万円ではなく106万円未満であること |
また、扶養を受ける配偶者が障害者の場合は、受給している障害年金を含めた年収が180万円未満までの場合、第3号被保険者の対象になります。
- 雇用保険の失業保険
- 健康保険の傷病手当
- 健康保険の出産手当金
- 障害年金
年金受給者の妻は扶養になれるの?
結論、扶養される配偶者が年金受給者であっても、第3号被保険者になれる場合があります。
それは「障害年金」の受給者である場合のみです。
障害年金であれば、年金を受け取りながらパートをしていても、年金の扶養の対象になります。

ただし、第3号被保険者の年齢制限が20歳以上60歳未満であることから、老齢年金の受給者は年金の扶養対象にはなれません。
パートと年金の手続き
パートをしながら夫の年金の扶養である第3号被保険者になるためには、配偶者の勤務先を通して手続きを行います。

税金、健康保険、会社の扶養手当などの手続きと同時に行う会社も多いので、パート年収を減らして扶養に入ることになった場合など、速やかに届け出ましょう。
家計を支える配偶者が第1号被保険者である自営業者の場合、年金と健康保険に関する扶養の制度がありません。
配偶者が会社員から自営業になった場合など、扶養される側も忘れずに「第1号被保険者」になる手続きを、役所の窓口で行う必要があります。
年金の扶養から外れる場合の手続き
年金・健康保険など、社会保険の扶養から外れる場合も手続きが必要です。
下記のような場合に、扶養ではなくなります。
- パート先の社会保険に加入するとき(自分が第2号被保険者になるとき)
- 自分が自営業者になるとき(自分が第1号被保険者になるとき)
- 第2号被保険者の配偶者と離婚したとき
- 第2号被保険者の配偶者が退職したとき
- 第2号被保険者の配偶者が65歳を超えたとき
- 第2号被保険者が亡くなったとき
上記のような場合には、第2号被保険者である配偶者の側への手続きと、自分の年金の手続きの2つを行う必要があります。
会社員・公務員の配偶者側の手続き
生計を支える配偶者が会社員や公務員の場合は、上記の理由で配偶者が扶養から外れる場合には、勤務先への申告が必要です。
年金と健康保険は扶養の条件が同一のため、扶養を外れる際には健康保険証を返却します。
パート本人の手続き
扶養に入っていた本人が扶養から外れる場合は、自身のパート先で社会保険に入る手続きを行います。
フリーランスなどの自営業者になる場合は、自治体の窓口で国民健康保険と国民年金に加入する手続きをする必要があります。

第2号被保険者の場合は、勤務先が手続きを促してくれますが、第1号被保険者の場合は役所に出向く必要があり、届け出が遅れて未納期間が生じるとデメリットが生じるのでご注意ください。
必要な届出を行わず、年金記録上で第3号被保険者のままになっていることが後で判明することが問題となっています。これを「第3号被保険者の不整合記録問題」といいます。
不整合記録がある場合、本来届出をすべき期限から2年以上経過すると保険料の納付が受け付けられず「未納期間」が生じます。
その結果、将来受け取る年金額が少なくなったり、受給資格期間を満たさず年金が受給できなくなる可能性があります。
※受給資格期間
・老齢年金:10年以上、国民年金(厚生年金)に加入して保険料を納めていること
・障害・遺族年金:加入期間の3分の1以上の期間における保険料未納がないこと
第3号被保険者が60歳になったら待ち受けている事
60歳になると、第3号被保険者の資格を喪失します。
60歳になれば、自動的に第3号被保険者の資格を喪失しますので、特に手続き等は不要です。
国民年金の義務も60歳までなので、何もしなくても問題はありません。ただ、何もしなければ基礎年金の支払期間も60歳で終了です。

老齢基礎年金の受給金額はその加入期間によって満額から割り引かれる仕組みです。20歳から60歳までの480か月のうち、未納の期間があれば満額は受け取れないんです。
少しでも受給額を増やしたい場合は、下記の方法がおすすめです!
国民年金の任意加入
未納期間や免除の減額があり、年金額を満額受け取れない場合、少しでも年金額を増やすには60歳以降65歳までの間、国民年金に任意加入することができます。
60歳以降も保険料の納付済期間を増やすことができれば、その分老齢基礎年金の額が増えます。
保険料は第1号被保険者と同額です。
一方、任意加入では、さかのぼって納付することはできません。また、通算の納付月数が480月を超えて納付することもできません。

60歳を迎えて、480か月に納付期間が満たない時は、60歳から65歳までの任意加入で補填できるというわけね!
付加年金で年金額を増やす
「付加年金」とは、国民年金保険料に月400円を上乗せして支払うことで、200円×付加年金の保険料納付月数の分、年金を上乗せして受け取れる制度です。
国民年金の任意加入期間に限り、付加年金に入ることができます。
60~65歳までの5年間付加年金に加入したとすると、2万4,000円の付加年金保険料になりますが、それによって毎年1万2,000円年金の受取金額を増やせます。

年金受け取りの3年目以降から、支払金額を超えるから得になるわね!
繰り下げ受給
年金の受給開始は原則65歳からですが、1カ月単位で受取を遅らせる「繰り下げ受給」と言う制度があります。
現状の制度では、1カ月繰り下げるごとに年金額が0.7%増加しますので、70歳から受給開始にすると、年金額は最大42%増やすことができます。
今からできる、パートの年金対策
1か月でも自分で厚生年金に加入しよう
老齢基礎年金(国民年金)を受け取るには、年金保険料を納めた期間と保険料免除期間を合算して120か月以上必要です。
老齢基礎年金を受け取る要件を満たしていれば、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上でもあれば、老齢厚生年金を受け取ることができるんです!

厚生年金の加入期間が10年必要ってわけじゃないのね!
厚生年金保険料や厚生年金の受取額は、標準報酬月額により決まります。保険料は会社が半分負担してくれますね。
給与が増えると厚生年金保険料や受け取り年金額も増えますので、厚生年金の加入期間が長くなればなるほど、将来受け取る年金も増えます。
月額にすれば大きな金額ではないかもしれませんが、一生涯受け取続けることができるので、トータルの金額は長生きするほど多くなります。
自分の保険としても機能する年金
また、障害年金は、第3号被保険者では「障害基礎年金」のみです。
厚生年金に加入して1年以上、厚生年金加入の時に初診日があれば、障害基礎年金に加えて「障害厚生年金」も受け取れます。

今後、病気やけがなどで働けない障害を負ったときの保険として、厚生年金が機能するのね!やっぱり、自分で年金を払うメリットって、精神的な安心の面でも大きい気がするわ。
寿命も延びているしね。
まとめ
第3号被保険者として、保険料を支払わずに国民年金の対象になるのは、納付期間には得をしているように感じます。
ただ、人生100年時代と言われ、女性の寿命の方が長い現状を考えると、年金を受給して生活する期間は決して短くはありません。
長生きしない可能性もありますが、途中で病気や障害を負うリスクもあり、結局損得だけでは語れないのが年金制度です。
制度もどんどん改正され、自分が将来受け取れる金額も定かではありません。
ただ一つ言えることは、先のことは誰にも分らない。だからこそ、年金制度だけに頼らず、自分で将来の年金代わりになるような資産を今から準備しておくことが大切だということです。
自分で稼げるスキルを身につけることや、長期投資などで将来の資金を準備しておくのがおすすめです。

私はNISAで老後資金を積み立てています!
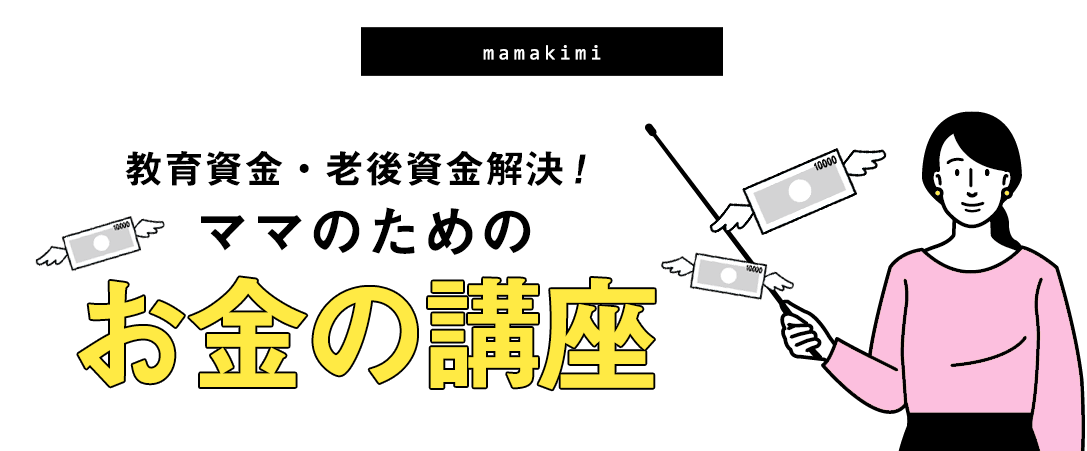


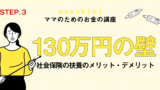
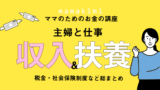


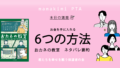
コメント