
万が一のけがや病気で働けなくなったら?傷病手当金だけでなく、障害年金の給付もあります!日本の福祉は素晴らしい!
「年金」と言えば、65歳以上になったらもらえる「老齢年金」を思い浮かべる人が多いと思いますが、実は受け取れる”年金”はこの老齢年金だけではありません。
条件によって「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができます。

年金って支払う保険料は一つなのに、「老齢」「障害」「遺族」の3つの給付のパターンがあるってわけね!
そうなんです!
このブログでは、ここまで一番メジャーな老齢年金について取り上げてきましたが、今回は「障害年金」について詳しく解説したいと思います。
- 障害年金は病気やけがで仕事が制限される場合に受け取れる
- 給付は現役世代でも受け取れる
- 障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」がある
- 病気やケガで初めて受診した日に入っていた年金によって受け取れる年金が変わる
- 精神障害でも障害年金は受け取れる
障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事や生活が制限されるようになった場合、受け取ることができる年金です。
受け取りの対象者は、現役世代も含めた年金の加入者です。※条件あり
障害年金にはも国民年金と同様、加入先により、「障害基礎年金」「障害厚生年金」 の二種類あります。
病気やケガで初めての医療機関受信日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求することになります。
障害基礎年金について
障害基礎年金は、国民年金に加入している間や、60歳以上65歳未満(日本に住んでいて年金制度に加入していない期間)だけでなく、年金の加入義務が発生する20歳前に、 障害の原因となった病気やケガ の初診日があっても障害年金の支給の対象になります。
障害年金の支給には、法令により定められた障害等級表(1級・2級)の障害状態であると認められる必要があります。
障害厚生年金 について
傷害の原因となる病気やけがの初診日において厚生年金に加入していた場合には、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が受給できます。
障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、傷害基礎年金に上乗せのかたちになりますが、障害の状態が2級未満の障害のときは3級の障害厚生年金が支給対象となります。
また、厚生年金では、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるより軽い障害が残った場合は障害手当金(一時金)が受給できます。

障害厚生年金の方が、3級でも支給があったり、傷害手当金をもらえたり、手当ても上乗せされて手厚いってことなのね!「初診日」の段階でどうだったのかがポイントね!
障害年金を受ける要件
障害年金を受けるためには、下記のような条件を満たしている必要があります。
次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが障害年金給付には必要です。
①初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間、保険料が納付または免除されている
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
障害認定の要件
障害年金は、初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)、未成年に場合は20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合を「障害認定日」とします。
ただし初診日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、例外的にその日を「障害認定日」とします。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
出典:日本年金機構
傷害の等級の認定基準
障害年金は、認定される等級によって金額が異なります。
重度であればあ支給される金額も多くなります。
障害等級の認定は、市区町村の年金にかかわる組織(年金事務所や国民年金課)が、厚生労働省の認定基準に基づいて決定しています。
| 障害等級 | 認定条件 |
|---|---|
| 1級 | 身体の障害または病状により、他人の介助を受けなければ日常生活を送れない状態。 |
| 2級 | 他人の介助が必ずしも必要ではないが、体の障害または病状により労働できない状態。 |
| 3級 | 傷病が治らず、労働に著しい制限を受ける状態。 |
障害等級を認定する際は、生活のうえで他者の介助が必要かどうかが重視されています。
障害基礎年金の支給額
障害年金は障害等級ごとにその支給額の計算方式が異なり、下記のとおりとなっています。
| 障害等級 | 計算式 |
|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 780,100円×1.25(等級倍率)+子の加算 |
| 障害基礎年金2級 | 780,100円+子の加算 |
障害基礎年金の場合は、3級以下の人は受給できません。
また、障害基礎年金の対象になる人は、扶養する子供の人数分の支給額を加算してもらえます。
扶養する子供が18歳未満の場合は、障害基礎年金の支給額をひとりあたり最大224,500円まで加算があり、扶養する子供の人数ごとの加算額は以下のとおりです。
| 人数 | 加算金額 |
|---|---|
| 第1子 | 224,500円/年 |
| 第2子 | 224,500円/年 |
| 第3子以降 | 1人あたり74,800円/年 |
3人目以降の子供は、何人増えても第3子と同じ金額が支給されます。
扶養する子供が障害等級1級または2級の認定を受けている場合は、20歳の誕生日を迎えるまで加算額を受け取れます。
障害基礎年金でもらえる金額例は下記のようになります。
| 障害基礎年金1級 | 障害基礎年金2級 | |
|---|---|---|
| 子供0人 | 975,125円/年(月81,269円) | 780,100円/年(月65,008円) |
| 子供1人 | 1,199,625円/年(月99,968円) | 1,004,600円/年(月83,716円) |
| 子供2人 | 1,424,125円/年(月118,760円) | 1,229,100円/年(月102,425円) |
| 子供3人 | 1,499,925円/年(月124,993円) | 1,303,900円/年(月108,658円) |
| 子供4人 | 1,574,725円/年(月131,227円) | 1,378,700円/年(月114,891円) |
上記は、障害基礎年金で受給できる金額の目安なので、厚生年金に加入している場合はこの金額にさらに上乗せされた金額が支給されます。
厚生障害年金の支給額
厚生障害年金は、前年度の収入×加入者期間×障害等級によって支給金額が異なります。
障害等級ごとに障害厚生年金の計算方式は下記の通りです。
| 障害等級 | 障害基礎年金(年間) | 障害厚生年金(年間) |
|---|---|---|
| 1級 | 977,125円+子の加算 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 (224,500円) |
| 2級 | 781,700円+子の加算 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 (224,500円) |
| 3級 | ー | 報酬比例の年金額(最低保障額586,300円) |
障害厚生年金には 586,300円の最低保障金額があり、年金加入期間が短い人の支給金額が確保されています。
最低保障金額は、障害基礎年金と合算した支給額が586,300円に満たない人に適用されます。
厚生年金における報酬比例年金額の目安は等級ごとに異なり、下記の通りです。
| 障害等級 | 報酬比例の年金額(年間) |
|---|---|
| 1級 | 約96万円〜約192万円 |
| 2級 | 約72万円〜約144万円 |
| 3級 | 約12万円〜約72万円 |
より正確な受給額が知りたいという場合は、ファイナンシャルプランナーの無料相談などで正確に見積もってもらうのがおすすめです。
精神障害と年金
「障害年金」と言うと、例えば交通事故で四肢を失った、視力を失った、人工透析を行っているなど、身体的な障害でもらえる年金と思われがちですが、実は精神障害も障害年金を受給するための条件の1つである障害等級が定められています。
- 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状 況等により、総合的に認定するものとする
- 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級とする
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級とする
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級とする
- 認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する
- 精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する
出典:日本年金機構 障害認定基準
うつ病と障害年金
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する とされているように、うつ病などの精神疾患でもその対象となります。
うつ病で障害年金を受け取る場合も、「初診日が存在する」「一定以上の障害である」「保険料の要件を満たしている」の3つの条件を満たしている必要があります。

逆にこの3つの条件が満たされていたら、傷害が精神疾患であっても障害年金を受ける権利があります。辛いうつ病で仕事に行けないなどの場合も、年金の対象になるのです。
精神障害者手帳の級と年金
一定以上の障害状態を認定する際は、その認定は、市区町村の年金にかかわる組織(年金事務所や国民年金課)が、厚生労働省の認定基準に基づいて決定しています。
一方厚生労働省は、「障害者保健福祉手帳」も等級ごとに発行しています。
ただ、この障害者手帳と障害年金は同じように等級を用いているのですが、制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なります。
そのため、例えば障碍者手帳の等級が3級でも、傷害年金の等級が2級になるなど、別物となります。
精神障害での障害年金受給は難しい?
精神障害者手帳と障害年金の判定基準を比較すると、障害年金のほうが認定対象となる精神疾患の範囲が狭くなっています。
たとえば、パニック障害は精神障害者手帳の交付対象になりますが、障害年金では対象外です。
等級の基準を見ても3級の基準が大きく異なり、障害年金では労働の制限が条件となっています。
また、診断書の記入の仕方なども審査に大きく影響を与えるため、障害年金の相談は障害年金に詳しい社会保険労務士に相談すると良いと言われています。
まとめ
老齢年金ほど有名ではない障害年金ですが、万が一のけがや病気で傷害を負ってしまった時、これからの暮らしを支えてくれる大事な制度ですね。
とはいえ、家族にもある程度収入があれば障害基礎年金でも十分な足しになりますが、もし専業主婦で小さな子供を抱えていて働けない場合などは、これではやっぱり生活には不十分ですよね?
かかる費用に対して受け取れる給付の差額分は、貯蓄や私的保険なども活用して備える必要があります。
大黒柱が働けなくなった家族の状況、家族の年齢によって、受給期間や内容が変わってきますので、いざというときの生活が成り立つのかどうか、こういった公的保証の金額はしっかり計算しておくに越したことはありません。

そうはいっても、素人にそんな計算できないわ、、、。困ったわね、、、。
家族に必要な保障額や、貯蓄や保険での備え方の的確なアドバイスが必要な場合は国家資格を持つ、ファイナンシャルプランナーに相談するのが一番正確で手っ取り早いです。
今は、無料で相談を受け付けているFPなども増えてきているので、ぜひそう言ったサービスを活用するのがおすすめです。

ちなみに障害年金は20歳以上に初診日があれば所得制限がないので、働きながらでも受給できます!
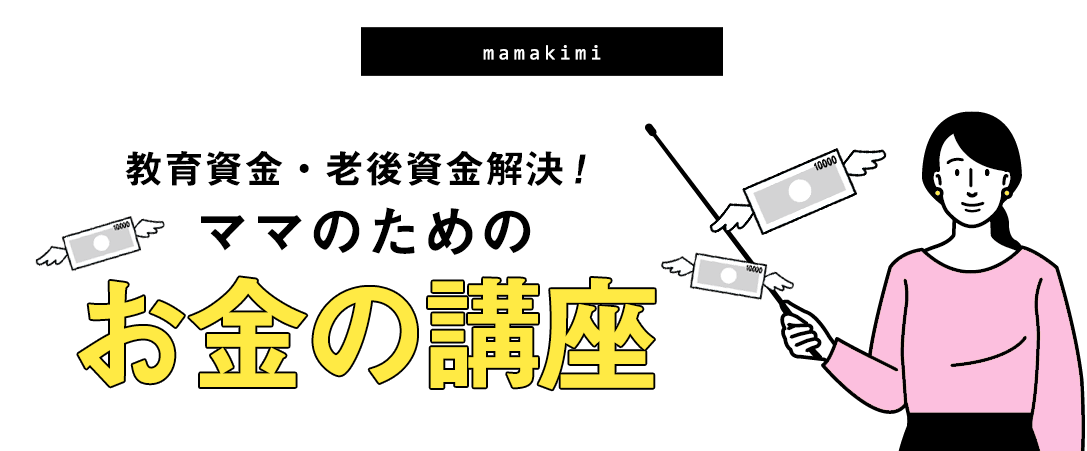
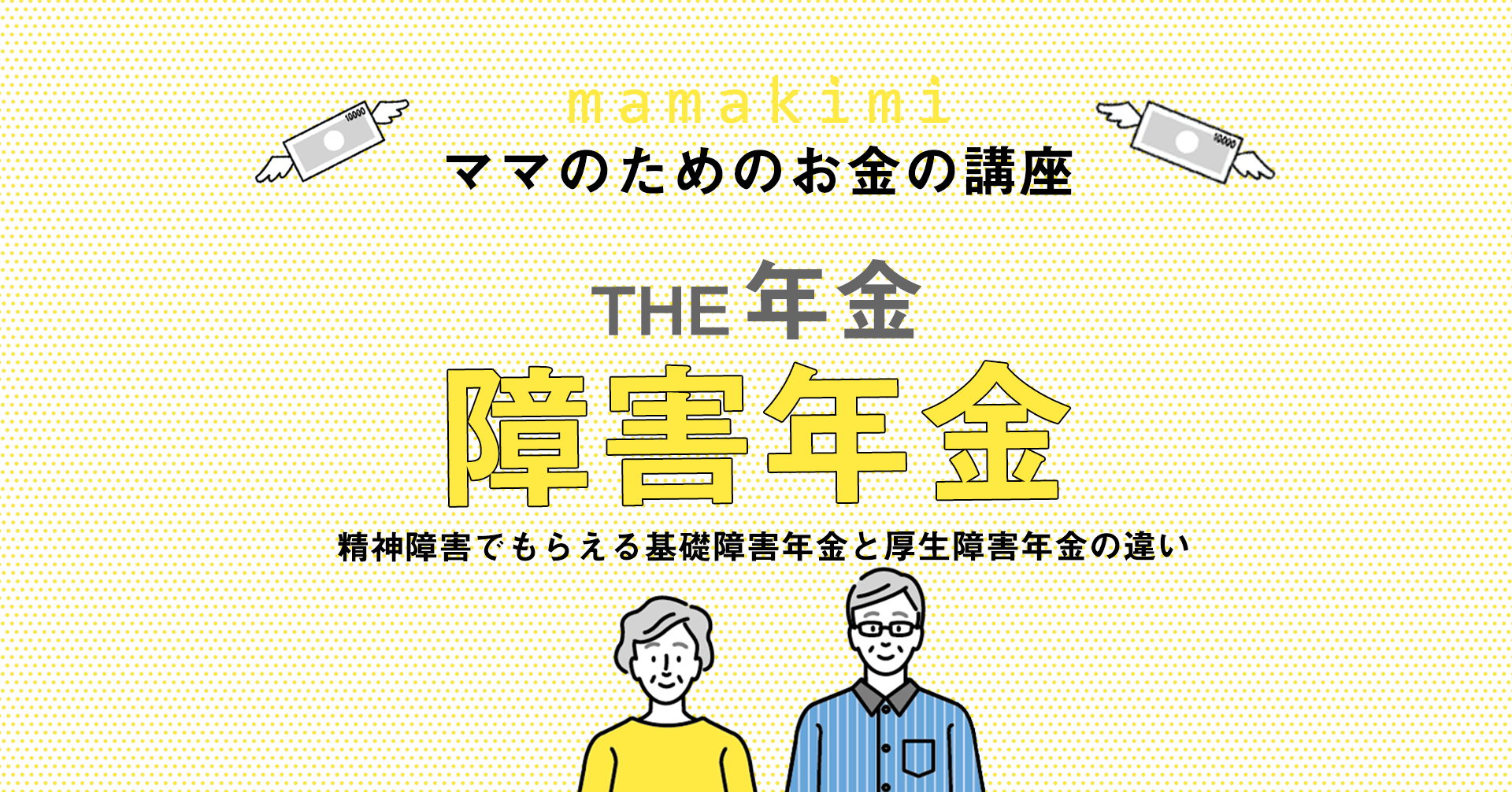
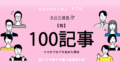
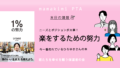
コメント