以前就学援助制度について、制度の概要をご紹介し、反響を呼びました。
住民税の非課税家庭でもないし、自分が就学援助制度の対象とは知らなかったという人が、援助の存在を知って申請してみたなど、個人的にメッセージも届いています。
そんな中で、実際に2年前からコロナの影響でパートを失って収入が減った、3人の姉妹を育てるママさんのお話を聞くことができました。
申請方法や、申請時の理由の記入例、学校での書類のやり取りなど、これから就学援助制度を受けようか検討されている方が気になるであろう内容を、インタビューし、今回記事にまとめました。
今回就学支援制度のリアルを教えてくれる方
今回お話を聞かせていただいたのは、関東にお住いの30代後半のご夫婦です。
現在小学2年生の双子の女の子と、年中になる女の子の3人姉妹を育てていらっしゃいます。
2年前まで近所の実家に子供を見てもらい、週に3日パートに出て年間90万円ほどの収入がプラスであったそうですが、コロナの影響でパートがなくなり、現在は旦那様の年収約500万で家計を支えています。
持ち家ではなく、賃貸暮らしとのことです。
就学援助は、2年前の双子の姉妹が入学説明会時にもらってきた書類の中にあり、申請してみたところ通って、入学準備金などを受けとることができたそうです。

双子ちゃんの入学と言うこともあって、倍かかる費用を就学援助金で賄えたのは大きいですね!
就学支援制度について質問してみました
Q.就学支援制度の申請時に悩んだことはありますか?
就学支援制度を受ける前に心配したことは、もし申請が通って、支援金を頂いたり、給食費が免除になったことが、クラスのお友達などにばれて、子供たちが肩身の狭い思いをしないかどうかということだったそうです。

有難いけど、援助を受ける事で子供に何か影響が出ては、、、と悩んでしまう気持ちすごくわかります!
Q.実際に周りに知られたり先生から冷遇されたりしましたか?
担任の先生は、生徒の家庭状況を把握するために、就学援助制度を利用していることは知っているそうですが、保護者や子供に対してそのことを言及することは一度もなかったそうです。
まだ小さいので、周りの子に知られるどころか、本人たちも気が付いていません。
現在はコロナの影響もあり、就学援助制度の利用率は15%程度に上るそうです。
30人クラスに換算すると、4,5人はいる計算になります。
ただ、私もそうですが皆さんはクラスで誰が、学年で誰が就学援助制度を利用しているか知っていますか?
自分が知らないということは、自分が受けても誰にも知られないということです。
Q.申請書や通知決定のやり取りと学校の対応はどのような形でしたか?
新1年生時の申請書は、入学前の集団検診の時に、他の諸々の書類と共に提出する機会があったそうです。
決定通知書については、役所の方から郵送で送られてきたので、学校を通すことはなかったとのこと。
2年生に上がってからは、継続の書類を封筒入りで娘さんたちが持って帰ってきたので、記入して封筒に入れて持たせたそうです。
娘さんたちによると、担任の先生に直接事務室に持って行くように言われ、事務室の先生に手渡したようです。
この年の決定通知書も、役所の方から郵送で送られてきたとのことです。

このやり取りなら、周りの友達や子供自身(小さいうちは)にも知られることは無いわね。教育委員会の方も、個人情報の取り扱いや生徒や家庭への配慮について通達しているだけあるわ。
Q.就学支援制度の申請理由に記入したこと(例)
就学支援制度の申請時の書類と、継続書類ともに、申請の理由を記入する欄があります。(各自治体による)
- 生活保護を受けている
- 児童扶養手当を受けている
この場合は理由の記入は必要ないのですが、その他の場合は失業や給食など経済状況の説明が必要で、どう書いたらいいのか迷ったそうです。
実際に記入したのは、「コロナで妻のパート収入がなくなり、世帯年収が減少したため」のようなことだったそうです。
客観的に見てわかるように、率直に理由を書けばよさそうです。
- 妊娠のため妻が離職し、世帯年収が減った
- 世帯主の会社が倒産したため無職状態にある
- コロナの影響で収入が減ったため
- 病気で休業中であるため
自治体が給与状況は把握しているため(もしくは源泉徴収などを提出する場合もある)、収入が少ない理由を補足的に記入すればよいと思います。
基本的に、可否に関わるのは家族の人数、持ち家か賃貸か、それによって定められた年収基準だからです。

こちらのご家族の場合は、5人家族で賃貸なので、年収550万円~660万円(所得400~500万円)くらいが就学援助制度を基準となっているので、審査に通ったわけです。記入する理由はそれほど悩む必要はないかと思います。
Q.就学援助金はどのように受け取っていますか?
就学援助金の入学準備の費用は、入学前の2月に振り込まれたそうです。
学用品費の方は、1年間学校で使った校外学習費や追加教材費など、本来口座から引き落とされる費用を差し引いて残った差額分を、新年度になってから前年度分を振り込みで受け取るそうです。
給食費に関しては、支払い自体が免除され、最初に全員が登録する口座から引き落とされないという対応だったとのこと。
その他、算数ブロックや植木鉢など、買う人と買わない人がいて、学校にお金を持参して購入するものは、皆と同じように購入するそうです。
その金額は、翌年度初めに残金を振り込まれる学用品費で賄えるとのこと。

現物支給があったり、支払って後から清算する自治体もあるようですが、こちらのご家族のようなパターンだと持ち出しが少ないので有難いですよね。
Q.就学支援制度を受けて後悔したことはありますか?
今のところ後悔していることは無いそうです。
最初は、やはり住民税非課税家庭でも生活保護でもない、年収500万円と言う一般家庭でありながら、自治体から支援金を受け取ることに引け目を感じていたそうですが、「制度の対象になる=受ける権利がある」という私のブログ記事の一文を読んで、お子さんたちのために有難く使わせてもらおうと思ったそうです。
そのことがきっかけで、就学援助を迷っているご家庭にとって役に立つ情報提供にご協力くださることになりました。
まとめ
就学援助制度は、家庭のプライバシーや子供の差別を受けないように、学校の先生・学校の事務員さん・自治体・教育委員会などが、申請や書類の行き来にはかなり配慮されているので、周りに知られる心配は不要だということ。
そして、考え方は人それぞれですが、「制度の対象になる=受ける権利がある」ということで、不正受給でもなんでもありません。
コロナで収入が減った、子供が多いので少しでも将来の貯蓄を増やしておきたいなど、現在と今後の子育てのために、ありがたく受け取ってもいいのではないかと思います。
これから入学を迎える小さなお子さんをお持ちのご家庭でも、就学援助制度があることや、入学準備やラン活など、上手に家計をやりくりできる方法を知っておくことが大切ですね。
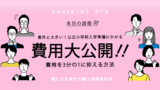

当ブログでは、インタビュー(匿名)で、情報を提供下さる方を随時募集しています!コメント欄やInstagramのメッセージからご連絡ください♡
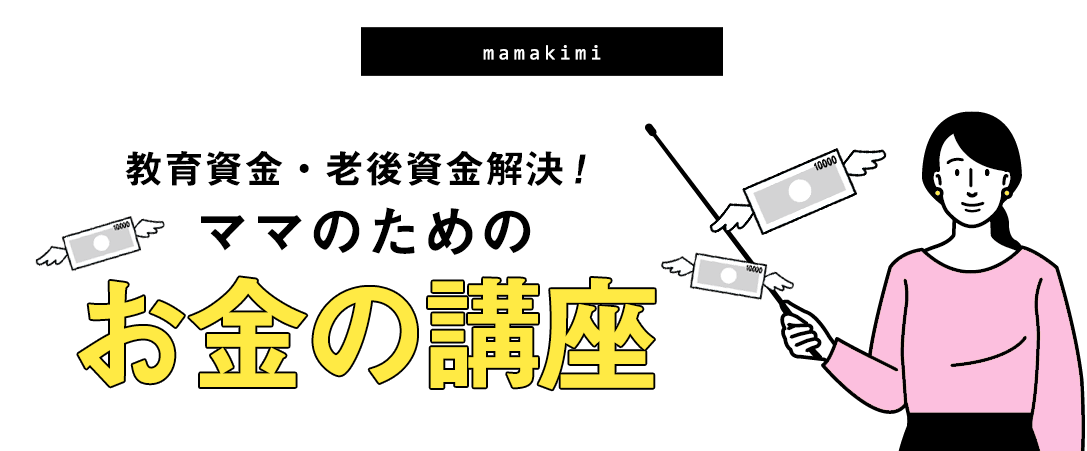
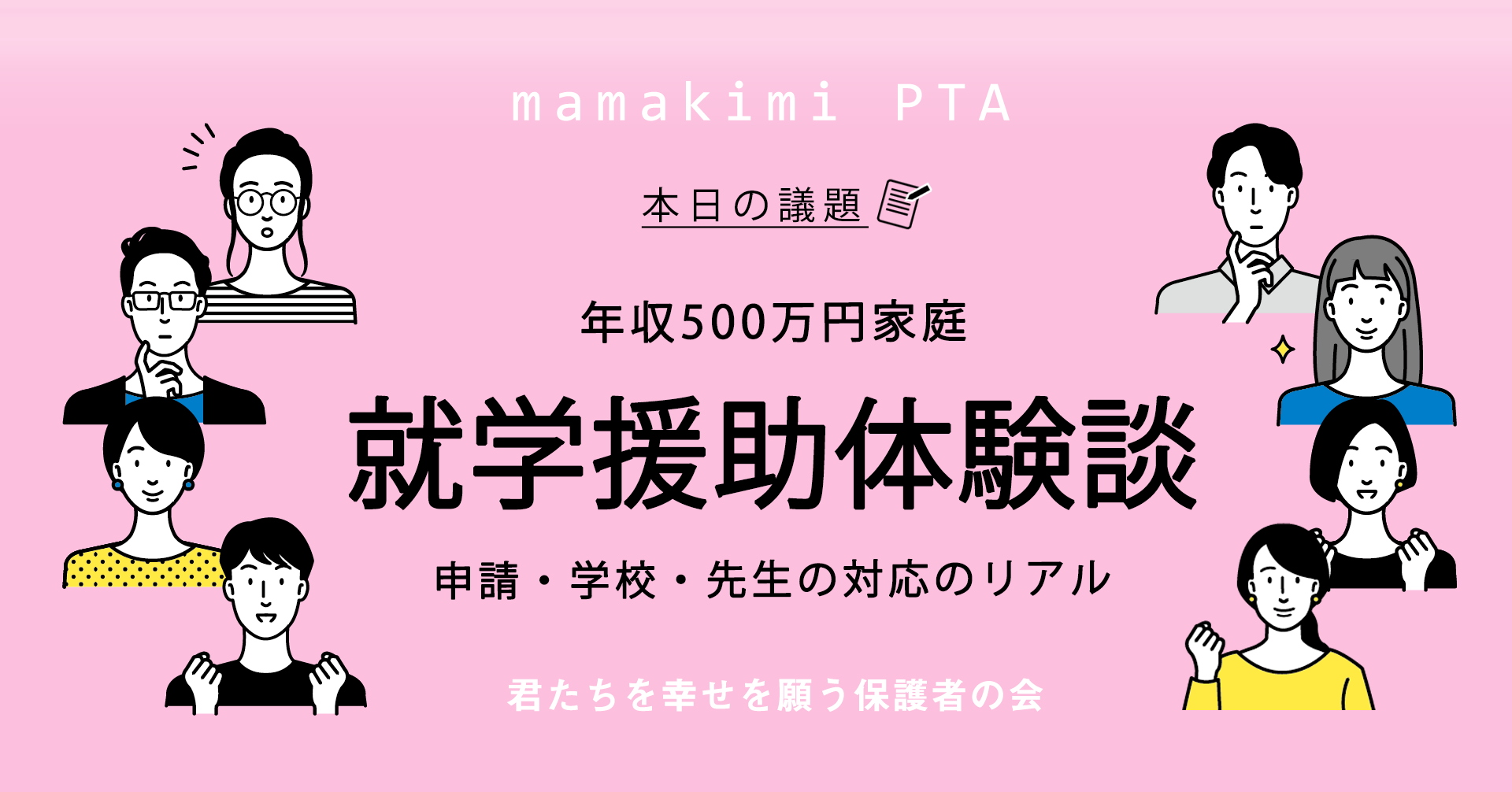
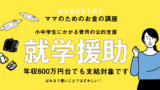
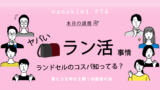
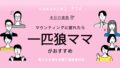
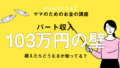
コメント